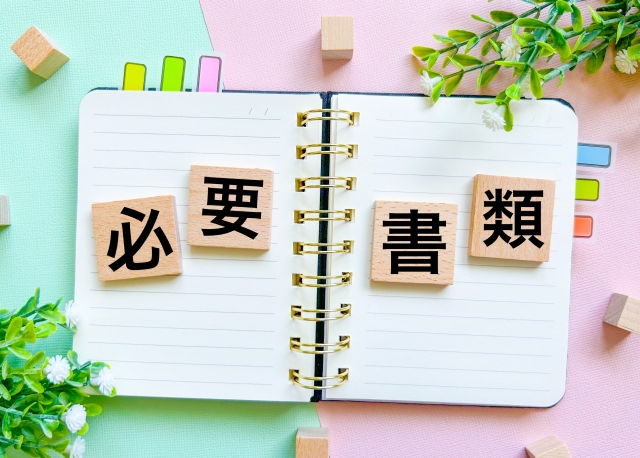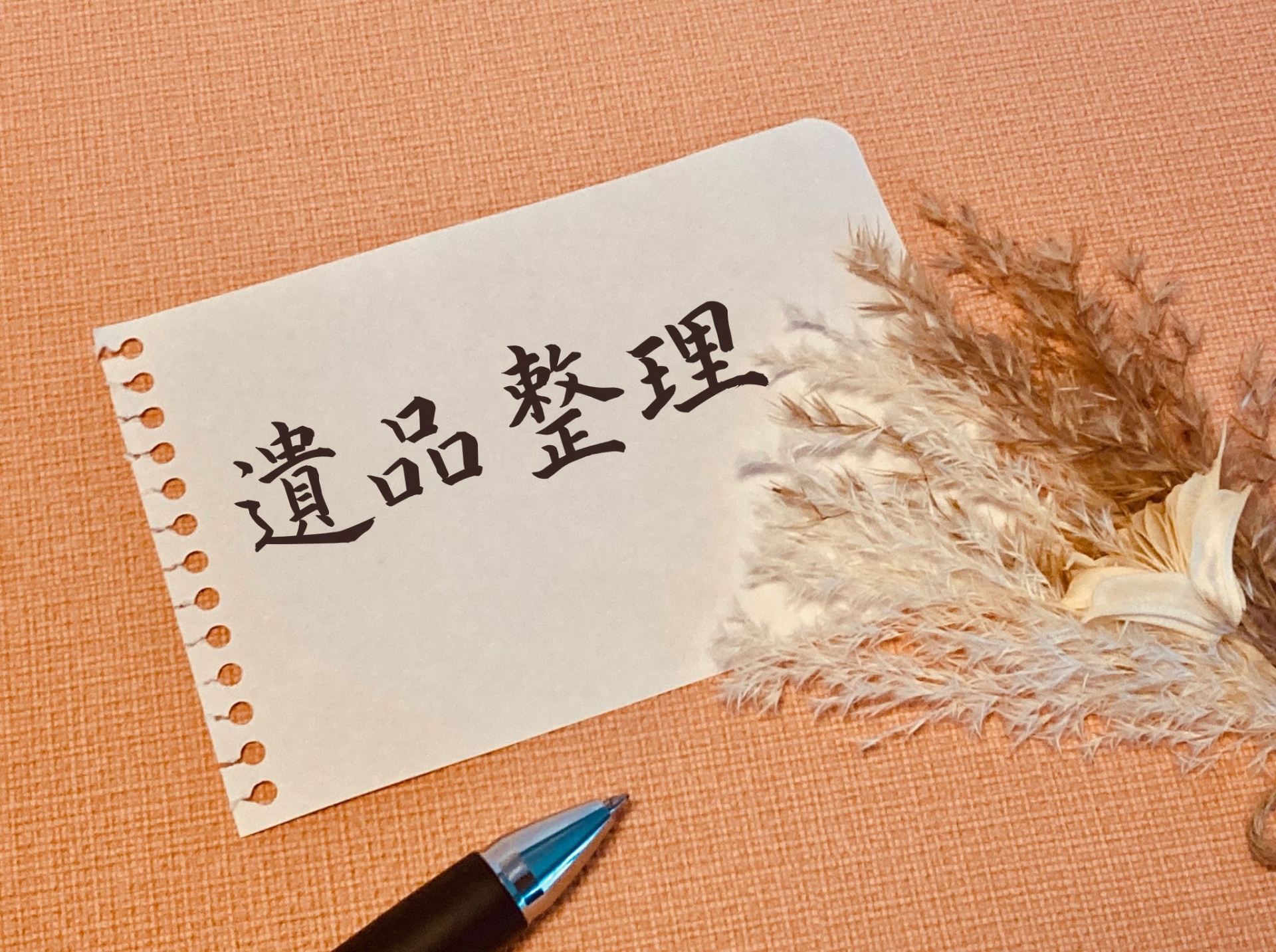現場ブログ
解体工事の境界線トラブル回避ガイド|工事前の確認方法とブロック塀・越境物の対処法

こんにちは!岡山の解体専門業者の株式会社アライブです。
「いざ家の解体を決めたけれど、お隣さんとの土地の境目って、正確にはどこなんだろう?」「境界線上にあるこの古いブロック塀、うちで勝手に壊していいものなの?費用は折半?」「解体作業の邪魔になる、お隣の木の枝が伸びてきているけど、どうすれば…」このように、解体工事を具体的に進めようとすると、普段はあまり意識することのなかった「土地の境界線」に関する様々な疑問や不安が、大きな心配事として浮かび上がってくるものです。
この記事では、そんな皆様の不安を解消するために、私たち解体のプロフェッショナルが、円満な解体工事の生命線とも言える「境界線」の確認に特化し、その具体的な確認方法から、トラブルになりやすい境界上のブロック塀の所有権問題、木の枝などの越境物への法的な対処法、そして何よりも重要な、境界線トラブルを未然に防ぐための信頼できる業者の選び方まで、詳しく、そして分かりやすく解説いたします。
この記事を最後までお読みいただければ、解体工事における「境界線」に関するあらゆる疑問が解消され、法的なリスクやご近所との無用な争いを未然に防ぎ、安心して工事に臨むための具体的な知識と手順が身につきます。岡山で、敷地の境界が曖昧で不安な方、隣地との間にブロック塀やフェンスがある土地の解体をご検討中の方、そして将来の土地売却なども見据え、この機会に境界を明確にしておきたいとお考えの賢明なご家族は、ぜひご一読ください。
目次
【なぜ重要?】解体工事で「境界線」の確認を怠ると起こる深刻な隣地トラブル事例
解体工事を始める前に、なぜ「境界線」の確認がそれほどまでに重要なのでしょうか。それは、境界線の認識が曖訪なまま工事を進めてしまうと、取り返しのつかない深刻な隣地トラブルに発展する危険性が非常に高いからです。「だいたいこの辺りだろう」という安易な思い込みは禁物です。ここでは、境界確認を怠った場合に起こりうる、代表的なトラブル事例をご紹介します。
1. 隣地の所有物を誤って解体・破損してしまうトラブル
これが最も深刻で、金銭的な問題に直結するトラブルです。
- 事例: 「境界線上にあるブロック塀は共有物だと思い込み、こちらの判断で解体してしまったら、後から『あれはうちの塀だった』とお隣さんから言われ、再設置費用を全額請求された」「境界線を越えて重機が入り込み、お隣の庭木や花壇、駐車場の床などを傷つけてしまった」
- 原因: 境界線の正確な位置や、境界上の構造物の所有権を確認せずに工事を進めたことが原因です。物理的な損害を与えてしまうため、関係の修復が非常に困難になります。
2. 敷地への無断立ち入り(越境)によるトラブル
悪意はなくても、作業員や重機が隣の敷地に入ってしまうことで、不信感や不快感を与えてしまいます。
- 事例: 「作業員が、近道だからと断りなくお隣の敷地を横切っていた」「足場を組む際に、一部がお隣の敷地の上空にはみ出していた」「解体で出た粉塵やガラ(破片)が、養生の隙間から隣の敷地に飛散した」
- 原因: 境界意識の低い業者や、作業員への教育不足が原因です。プライベートな空間を侵害されることは、誰にとっても大きなストレスとなります。
3. 所有権や費用負担を巡る紛争
特に、境界線上にあるブロック塀やフェンスの扱いは、トラブルの温床となりがちです。
- 事例: 「共有のブロック塀の解体費用は折半だと思っていたら、お隣から『うちは解体に同意していないので費用は払わない』と言われた」「解体後、新しい塀を建てることになったが、その種類や費用、設置位置を巡って意見が対立し、話が進まない」
- 原因: 工事の前に、費用負担や解体後の計画について、双方で明確な合意を書面で交わしていなかったことが原因です。
4. 解体後の土地活用・売却への支障
工事中のトラブルだけでなく、将来にわたって影響が尾を引くケースもあります。
- 事例: 「解体工事がきっかけで境界が不明確になり、いざ土地を売却しようとしたら、隣人との間で境界の主張が食い違い、買い手が見つからなくなってしまった」「境界標を工事中に誤って動かしてしまい、復元するために高額な測量費用が必要になった」
- 原因: 解体工事を機に境界を明確にしておく、という視点が欠けていたことが原因です。
以前、あるお客様がご自身で「お隣さんとは長年の付き合いだから大丈夫」と、境界の確認をされないまま解体を進めようとされたことがありました。私たちは、「親しい仲だからこそ、後で揉めないように、きちんと形に残るもので確認しましょう」とご提案し、一緒に境界標の確認を行いました。すると、お客様が思っていた位置と、実際の境界標の位置が少しずれていることが判明しました。あのまま工事を進めていたら…と思うと、今でも冷や汗が出ます。境界線の確認は、信頼関係を壊さないためにこそ、必要な作業なのです。
【工事前の必須作業】土地の境界線の確認方法は?境界標・公図・確定測量図の見方
解体工事を始める前の「境界線の確認」は、施主様と隣地所有者様、そして私たち解体業者が、三者で共通の認識を持つための非常に重要な作業です。では、具体的にどのようにして境界線を確認すれば良いのでしょうか。ここでは、ご自身でもできる確認方法から、最も確実な方法まで、ステップを追って解説します。
ステップ1:現地での「境界標」の確認
まず最初に行うべきは、現地で「境界標(きょうかいひょう)」を探し、確認することです。
- 境界標とは?: 土地の境界点を示すために設置された標識のことで、コンクリート杭、金属標(プレート)、プラスチック杭、石杭など、様々な材質・形状のものがあります。多くは、土地の角の部分に埋め込まれています。
- 確認方法: ご自身の敷地だけでなく、隣接する土地の所有者様にもお声がけし、必ず双方立ち会いのもとで一緒に境界標の位置を確認することが重要です。一方的な確認や判断は、後のトラブルの原因となります。「この杭が、うちと〇〇さんの土地の境の目印で間違いないですよね?」とお互いに確認し合うプロセスが大切です。
ステップ2:法務局での資料確認
境界標が見当たらない場合や、より客観的な資料で確認したい場合は、管轄の法務局で以下の書類を取得します。
- 公図(こうず): 土地の大まかな位置や形状、隣接関係が分かる地図です。ただし、明治時代の測量を基にしている場合も多く、精度は必ずしも高くないため、あくまで参考資料として捉える必要があります。
- 地積測量図(ちせきそくりょうず): 土地の面積を算出するための測量図で、各境界点間の距離や、境界標の種類などが記載されています。比較的新しい年代に作成されたものであれば、信頼性は高いと言えます。
ステップ3:最も確実な「確定測量図」の有無を確認
過去にその土地を測量したことがある場合、お手元に「確定測量図(境界確定図)」という書類がないか確認してみましょう。
- 確定測量図とは?: 土地家屋調査士という国家資格者が、隣接する全ての土地所有者と現地で立ち会い、境界を確認・合意した上で作成された、法的な効力を持つ非常に信頼性の高い図面です。
- 重要性: この図面があれば、境界に関するトラブルのほとんどは未然に防ぐことができます。もし、この図面が存在するなら、解体業者にその写しを渡すことで、非常にスムーズかつ安全に工事を進めることができます。
ステップ4:境界が不明確な場合の最終手段「境界確定測量」
境界標が見つからない、隣人との主張が食い違う、あるいは確定測量図がない、といった場合は、解体工事の前に、専門家である土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を行うことを強くお勧めします。費用はかかりますが(土地の形状や隣接地の数により20万円~80万円程度)、ここで境界を曖昧にしたまま工事を進めるリスクを考えれば、必要な投資と言えます。この測量により、法的に有効な新しい確定測量図が作成され、将来にわたって安心できる財産となります。
解体工事は、土地の境界を再確認する絶好の機会です。建物の解体を機に、土地の境界という「目に見えない資産」の価値を、しっかりと守り、明確にしておくことが、将来の安心に繋がるのです。
境界線上にあるブロック塀・フェンスは誰のもの?解体時の所有権確認と費用の話

解体工事における境界線トラブルの中で、最も発生頻度が高いのが、お隣との間にある「ブロック塀」や「フェンス」の扱いです。見た目だけでは、その所有権がどちらにあるのか、あるいは共有物なのかを判断するのは困難です。ここでは、境界上にあるブロック塀などの所有権の確認方法と、それに応じた解体時の費用負担の考え方について解説します。
ブロック塀の所有権は3パターン
まず、境界線上にあるブロック塀の所有権には、以下の3つのパターンがあることを理解しましょう。
- 自己の所有物: ブロック塀が、完全に自分の敷地内に建てられている場合。
- 隣地の所有物: ブロック塀が、完全に隣の敷地内に建てられている場合。
- 共有物: ブロック塀の中心が、土地の境界線の上に乗っている場合。
所有権の確認方法
では、この3つのうち、どのパターンに該当するのかを、どうやって確認すれば良いのでしょうか。
- ブロック塀の位置を確認する: まずは、境界標などを基にした境界線と、ブロック塀の位置関係を確認します。塀が完全に自分の敷地側にあれば①、相手の敷地側にあれば②、境界線をまたいでいれば③の可能性が高くなります。
- 基礎の形状を確認する: L字型の基礎を持つブロック塀の場合、その出っ張っている部分がある側が所有者、というケースが多いです。
- 過去の書類を確認する: 土地の購入時や、ブロック塀を設置した際の契約書、あるいは隣人との間で交わした覚書などがあれば、そこに所有権に関する記載がないか確認します。
- 隣地所有者へ確認する: 最も確実なのは、やはり隣地所有者様に直接確認することです。「この塀は、いつ頃、どちらが建てられたものかご存じですか?」と、過去の経緯を尋ね、双方の認識をすり合わせることが重要です。
所有権に応じた解体費用と同意の考え方
- ①自己の所有物の場合:
- 解体と費用: 原則として、所有者であるご自身の判断で、ご自身の費用負担で解体することができます。
- 注意点: ただし、たとえ自分の塀であっても、解体工事が隣地に影響を及ぼす可能性はあります。必ず事前に工事の旨を隣人に伝え、理解を得ておくことが、トラブルを避けるためのマナーです。
- ②隣地の所有物の場合:
- 解体と費用: これは相手の財産ですので、絶対に勝手に解体してはいけません。 もし、こちらの解体工事の都合で撤去が必要な場合は、相手の同意を得た上で、費用負担についても協議する必要があります。基本的には、撤去を要望する側が費用を負担するのが一般的です。
- ③共有物の場合:
- 解体と費用: 共有物であるため、必ず双方の同意がなければ解体することはできません。解体費用については、民法上は共有者が等しい割合で負担することになりますが、実際には、解体の必要性や、それによって利益を得る度合いなどに応じて、話し合いで負担割合を決めるのが一般的です(例:解体を強く望んだ方が7割負担する、など)。この合意内容は、必ず書面に残しておきましょう。
以前、あるお客様の解体工事で、お隣との間の古いブロック塀の撤去をご希望されました。私たちはまず、お客様と一緒に隣地の方へご挨拶に伺い、塀の所有権について確認しました。幸い、設置時の簡単な図面が残っており、共有物であることが判明しました。そこで、解体費用と、新たに設置するフェンスの費用について、両家で折半するという内容の覚書を作成し、双方が署名捺印した上で工事に着手しました。この一手間をかけたことで、費用負担に関する一切の不安なく、円満に工事を終えることができました。
お隣の木の枝や屋根が越境…解体工事の邪魔になる越境物の正しい対処法(民法改正も解説)
解体工事を進めるにあたり、もう一つ問題となりがちなのが、隣の土地からの「越境物」です。お隣の庭から伸びてきた木の枝や、建物の屋根のひさしなどが、こちらの敷地に侵入しており、重機の進入や足場の設置の邪魔になるケースがあります。このような越境物には、どのように対処すれば良いのでしょうか。勝手に切ったり壊したりすると、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
越境物への基本的な対処法
原則として、隣地から越境しているものであっても、それが木の枝であれ、建ものの一部であれ、所有権は隣地の所有者にあります。そのため、無断で切ったり、壊したりすることはできません。 もし、勝手に処理してしまうと、器物損壊罪に問われたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。
基本的な対処法は、まず隣地の所有者様に、解体工事の計画を説明し、「工事の安全上、大変申し訳ないのですが、越境している枝(または屋根など)を伐採(または撤去)していただけないでしょうか」と、丁重にお願いすることです。その際の費用負担についても、話し合いで決める必要があります。
【2023年4月施行】改正民法によるルールの変更点
ここで、特に「木の枝」の越境について、知っておくべき重要な法改正がありました。2023年4月1日に施行された改正民法により、木の枝の越境に関するルールが、より現実的なものに変わりました。
- 改正前: 越境した枝は、自分で切ることはできず、隣地の所有者に切ってもらうよう請求することしかできませんでした。相手が応じなければ、裁判を起こす必要がありました。
- 改正後: 以下の3つのケースに限り、隣地の所有者の同意がなくても、越境した枝を自分で切り取ることが可能になりました。
- 木の所有者に、枝を切るよう催促したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない場合。
- 木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合。
- 急迫の事情がある場合。(例:今にも枝が折れて、自分の家に被害が出そうな場合など)
この民法改正により、解体工事の際に、どうしても隣人と連絡が取れない、あるいはお願いしても対応してもらえない、といった状況でも、法的な手続きを踏めば、工事を進めやすくなりました。
ただし、「木の根」については、改正前から、発見した側が自由に切り取ることが認められています。
越境物への対処で最も重要なこと
たとえ法律上、自分で切り取ることが可能になったとしても、それが最善の策とは限りません。無断で枝を切ることが、隣人との感情的なしこりを残し、その後のご近所付き合いに悪影響を及ぼす可能性は十分にあります。
法的な権利を主張する前に、まずは誠実な対話を試み、円満な解決を目指す姿勢が何よりも大切です。解体業者も交え、工事の安全性確保のために協力をお願いするという形で、丁寧に話し合いを進めることが、最良の対処法と言えるでしょう。
以前、ある現場で、お隣の大きな木の枝が、解体する家の屋根に覆いかぶさっているケースがありました。私たちは、まずお隣の所有者様にご挨拶し、工事中の安全確保のために枝の伐採をお願いしました。その際、伐採にかかる費用は、工事の必要経費として弊社(施主様負担)で持つことをご提案しました。その結果、所有者様も快く承諾してくださり、スムーズに工事を進めることができました。相手への配慮と、こちら側の譲歩の姿勢が、円満な解決に繋がった事例です。
境界線トラブルを未然に防ぐ!信頼できる解体業者の選び方と相談時のポイント
解体工事における境界線トラブルは、一度こじれると解決が非常に困難です。だからこそ、こうしたデリケートな問題に、専門家として慎重かつ的確に対応してくれる、信頼できる解体業者をパートナーに選ぶことが、トラブルを未然に防ぐための最大の鍵となります。ここでは、境界線トラブルに強い優良な業者を見分けるためのポイントと、相談する際に伝えるべきことについて解説します。
境界線トラブルに強い優良業者の見分け方
- 現地調査の際に、境界線について業者側から確認があるか:優良な業者は、見積もり前の現地調査の段階で、「隣地との境界標はどこにありますか?」「境界線上にあるこの塀は、どちらの所有物かお分かりですか?」など、必ず境界線に関する確認を行ってきます。リスクを事前に察知し、管理しようという意識の表れです。逆に、境界について何も触れない業者は、注意が必要かもしれません。
- 慎重な作業計画と、リスクへの具体的な説明があるか:隣地との境界ギリギリでの作業や、越境物がある場合の対応策について、具体的な計画を立て、そのリスクと対策を丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。「大丈夫です、うまくやりますから」といった根拠のない自信ではなく、「この部分は手作業で慎重に進めます」「この越境物については、お隣様へのご説明が必要ですね」といった、具体的な説明があるかどうかがポイントです。
- 必要に応じて、他の専門家の協力を提案してくれるか:境界が不明確な場合や、所有権が曖昧な場合に、「念のため、土地家屋調査士に相談して、境界確定測量を行った方が良いかもしれませんね」といった、他の専門家の協力を提案してくれる業者は、非常に信頼性が高いと言えます。自社の利益だけでなく、お客様の将来的なリスクまで考えてくれている証拠です。
- 近隣への丁寧な説明とコミュニケーション能力:境界に関する問題は、最終的には隣地所有者様とのコミュニケーションに行き着きます。施主様に代わって、あるいは施主様と一緒に、デリケートな問題を感情的にならず、論理的かつ誠実に隣人へ説明できるコミュニケーション能力を持っているかどうかも、担当者を見極める重要なポイントです。
業者に相談する際に伝えるべきポイント
- 境界に関する現状と不安を正直に伝える: 「境界標が見当たらない」「お隣さんとは、昔から境界で少し揉めている」など、現在把握している状況や不安な点を、包み隠さず業者に伝えましょう。
- 境界に関する資料の有無を伝える: 確定測量図や、過去の覚書など、境界に関する書類があれば、その存在を伝え、提示しましょう。
- 解体後の土地利用計画を伝える: 解体後に土地を売却する予定があるのか、あるいは新築するのかによって、境界を確定させることの重要性が変わってきます。後の計画を伝えることで、業者もより的確なアドバイスができます。
私たち株式会社アライブは、解体工事の専門家であると同時に、地域社会の一員です。だからこそ、工事そのものの品質だけでなく、そのプロセスにおいて、お客様と近隣の皆様との間に、決してしこりを残さないことを最も大切にしています。境界線という、目には見えないけれど非常に大切な線を、全ての関係者で尊重し、確認し合うこと。それこそが、私たちの仕事の第一歩なのです。
まとめ
今回のコラムでは、解体工事を円満に進める上で避けては通れない「境界線」の問題に焦点を当て、その確認を怠った場合の深刻なトラブル事例から、具体的な確認方法、トラブルになりやすいブロック塀や越境物への対処法、そして何よりも重要な、信頼できる専門業者の選び方まで、詳しく解説してまいりました。
解体工事の成功は、着工前の「境界線の確認」という、地味で手間のかかる作業にかかっていると言っても過言ではありません。境界標の位置をお隣さんと一緒に確認すること、境界上のブロック塀の所有権を明確にすること、そして越境物については法律も理解した上で慎重に対処すること。これらの事前準備を丁寧に行うことが、後々の深刻な紛争を防ぎ、お客様ご自身の財産と心の平穏を守ることに繋がります。
そして、これらのデリケートな問題を円滑に進めるためには、技術力はもちろんのこと、境界問題に対する高い意識とリスク管理能力、そして近隣の方々への細やかな配慮とコミュニケーション能力を兼ね備えた、信頼できる解体業者をパートナーに選ぶことが不可欠です。
この記事が、これから解体工事を計画されている皆様にとって、境界線に関する不安を解消し、全ての関係者が納得できる、円満な工事を実現するための一助となれば幸いです。
株式会社アライブでは、岡山地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から舗装工事までおこなっております。私たちは、目に見える建物を壊す前に、目に見えない隣地との境界線を尊重し、確認することを最優先します。是非!解体の事なら株式会社アライブにお任せください!
その他のブログ記事/ OTHER BLOG /
岡山で解体のことなら
株式会社ALIVEへ
木造解体工事、鉄骨解体工事、RC解体工事、内装解体工事、アスベスト除去、プチ解体工事まで
安心してお任せください。地域密着・スピード対応!
お気軽にお問い合わせください。
住所:〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘368-3(国道250号線沿い)
電話番号:0120-812-181
受付時間:8:00〜19:00
定休日:なし
株式会社アライブの
スタッフ/ STAFF /

完全自社施工
だから安心
解体の事は何でも
ご相談ください