現場ブログ
畑や農地を処分するには?
「岡山で畑を処分したいけれど、どんな方法があるのか分からない…」「農地を売却したいけど、手続きが複雑そう…」そんなお悩みはありませんか?
本記事では、岡山で畑(農地)を処分する方法や活用法について詳しく解説します。農地法の規制や手続きの流れ、注意点についても触れながら、あなたに合った最適な方法をご提案します。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
岡山で畑の処分や活用を考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
目次
畑(農地)を処分したい場合の方法は?

畑を処分する方法には、主に以下の方法があります。
畑(農地)を売却する
農地を売却する際には、農地法による規制があるため注意が必要です。
農地法の規制
農地を売却するには、農地法の規制に従い農業委員会の許可を得る必要があります。特に農地を宅地として売却する場合は転用許可が必要で、手続きに時間がかかることもあります。
畑(農地)の価格の変動
農地の価格は、立地や利用目的によって大きく異なります。市街地に近い農地は高値で取引される傾向がありますが、農業振興地域内にある農地は価格が安くなることが一般的です。
手続きの複雑さ
農地の売却には、農業委員会の許可や法務局での登記手続きなど、多くのステップがあります。事前に専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。
農地中間管理機構を利用する
農地を手放したい場合、農地中間管理機構を利用する方法もあります。農業を希望する人や法人に農地を貸し出す仕組みで、売却が難しい農地の活用方法として注目されています。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した農地を手放したい場合、国に返納する「相続土地国庫帰属制度」を利用することも可能です。ただし、一定の要件を満たす必要があるため、事前の確認が必要です。
自治体に寄付する
一部の自治体では、農地の寄付を受け付けています。条件によっては受け入れが難しい場合もあるため、事前に自治体へ相談しましょう。
畑(農地)の活用方法
畑をそのまま手放すのではなく、活用するという選択肢もあります。
畑(農地)を貸し出す
農業をしたい人に貸し出すことで、固定資産税の負担を軽減しつつ収益を得ることができます。
農業以外の目的で活用する
太陽光発電
メリット
- 長期的な安定収益を得られる
- 遊休地を有効活用できる
デメリット
- 初期投資が高額
- 法規制や自治体の許可が必要
注意点
- 土地の傾斜や日照条件を事前に確認する
駐車場
メリット
- 比較的低コストで整備可能
- 安定した収益が見込める
デメリット
- 利用者が少ないと利益が出にくい
- 立地に左右される
注意点
- 近隣の交通量やニーズを調査する
資材置き場
メリット
- 初期投資が少なく済む
- 需要が安定している
デメリット
- 景観や環境面での制約がある
- 一部地域では許可が必要
注意点
- 近隣住民とのトラブルを避けるため事前に説明する
キャンプ場・グランピング施設
メリット
- 観光需要が高まっている
- 他の用途に比べて高収益が期待できる
デメリット
- 設備投資や運営コストがかかる
- 集客が必要
注意点
- 季節や天候の影響を受けるため、安定収益化が課題
ドッグラン
メリット
- ペットブームで需要が高い
- 維持管理が比較的容易
デメリット
- 立地によっては集客が難しい
- 近隣住民とのトラブルの可能性
注意点
- 騒音対策や衛生管理を徹底する
畑(農地)の処分や活用方法を検討する際のポイント
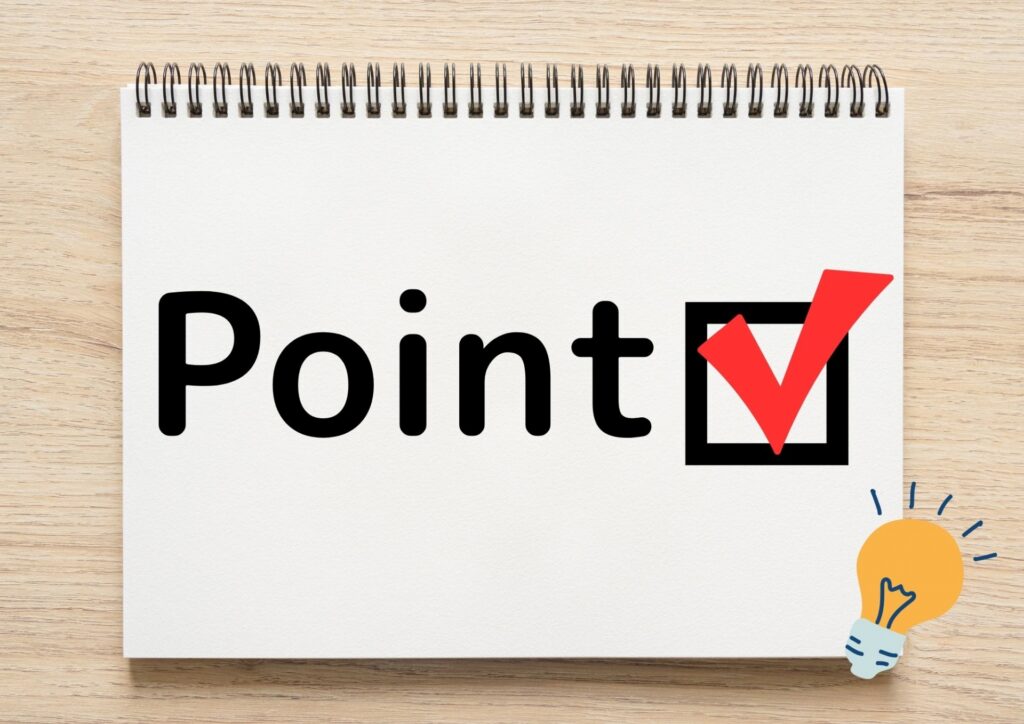
畑(農地)の特徴
地目や地勢、アクセスの良さを考慮し、適切な処分・活用方法を選ぶことが重要です。
地域全体の特性
周辺の土地利用状況や市場ニーズを把握することで、より有効な活用方法が見つかります。
費用対効果のバランス
初期投資や維持費、将来的な収益を比較しながら、最適な選択をすることが大切です。
畑(農地)の処分・活用における注意点
農地法の規制
農地を転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
税金
売却や賃貸による所得税、固定資産税などを事前に確認しましょう。
環境への影響
農薬や排水の管理を適切に行い、環境に配慮する必要があります。
周辺住民への配慮
騒音や景観の変化に対するトラブルを防ぐため、事前の説明や合意形成が重要です。
権利関係
相続や共有名義の場合、関係者全員の合意が必要になるため注意しましょう。
畑(農地)を処分・活用する際の具体的な流れ
畑を処分または活用するには、具体的な手順を踏む必要があります。ここでは、売却・賃貸・転用それぞれの流れを詳しく解説します。
畑(農地)を売却する場合の流れ
- 農地の現状を確認する
- 地目が「農地」かどうか登記簿謄本で確認する。
- 農業振興地域内かどうか調査する(農振地域内の農地は転用が難しい)。
- 水道や道路の接続状況を確認する。
- 農地法の許可を取得する
- 一般的に農地を売却する際には農業委員会の許可が必要。
- 農地転用を希望する場合は、都道府県知事の許可も必要になる。
- 売却先を探す
- 農家、個人、企業、不動産業者に相談。
- 農地として売却する場合、買い手は農地取得の要件を満たす必要がある。
- 売買契約を結び、所有権移転登記を行う
- 契約書を作成し、司法書士に依頼して登記手続きを進める。
- 引き渡しを行い、売却完了
- 売却後は確定申告で税金の申告を忘れないようにする。
畑(農地)を賃貸する場合の流れ
- 賃貸できるか確認
- 農地を貸すには、農地法に基づく「農地の賃貸借契約」を結ぶ必要がある。
- 農業委員会に届出を出し、適正な契約とする。
- 借り手を探す
- 農地を探している農家や新規就農者にアプローチする。
- 農地中間管理機構を通じて貸し出すのも選択肢。
- 賃貸契約を結ぶ
- 口約束ではなく、必ず契約書を作成。
- 賃料や貸借期間を明確にし、トラブルを防ぐ。
- 利用開始・管理
- 契約期間中、農地の管理状況を定期的に確認。
- 必要に応じて契約更新や修正を行う。
畑(農地)を転用する場合の流れ
- 転用可能か確認する
- 地目変更が必要な場合、農地転用許可を取得する。
- 農業振興地域に指定されている場合、除外申請が必要。
- 転用先の用途を決める
- 太陽光発電、駐車場、資材置き場など、用途に応じた計画を立てる。
- 各用途に応じた許可や届出を確認する。
- 申請手続きを行う
- 都道府県の農業委員会へ転用許可申請を提出。
- 許可が下りたら、工事や開発を進める。
- 転用後の管理・運用を行う
- 継続的な運営が必要な事業の場合、管理計画をしっかり立てる。
- 必要に応じて、税務や法務面の専門家に相談する。
岡山で畑(農地)を売却・活用する際の成功事例
事例1:農地を売却し、宅地として活用
岡山市内で代々受け継いできた農地を持つAさんは、農業を続ける後継者がいないため売却を検討。農業委員会に相談し、農地転用の許可を取得後、不動産業者を通じて売却。結果、住宅用地として高値で売却が成立し、スムーズに処分できた。
事例2:使っていない畑を駐車場に転用し副収入を得る
Bさんは、岡山市郊外にある農地の一部を利用して駐車場を設置。都市部からのアクセスが良く、月極駐車場として貸し出した結果、安定した収入源となった。
事例3:農地をキャンプ場として活用し、地域活性化に貢献
Cさんは、遊休農地を活用し、キャンプ場として事業をスタート。市や県の補助金を活用しながら整備を進め、地元の特産品を提供することで地域の活性化にもつなげた。
畑(農地)を処分・活用する際の費用と税金

主な費用
- 農地転用手続き費用:5万円~10万円
- 測量費用:10万円~30万円
- 売買契約の登記費用:10万円~20万円
- 開発費用(転用時):50万円~数百万円(用途による)
関係する税金
- 固定資産税:農地のままなら低税率だが、転用後は税負担が増える。
- 譲渡所得税:売却益が出た場合、所得税・住民税がかかる。
- 不動産取得税:転用後の用途によっては、新たに発生する可能性がある。
岡山で畑の処分・活用を成功させるためのポイント
- 事前に市場調査を行う
- 近隣の土地相場や需要を把握し、最適な売却・活用方法を選ぶ。
- 農業委員会や専門家に相談する
- 農地の売却や転用には専門知識が必要。プロのアドバイスを受けながら進めると安心。
- 長期的な視点で計画を立てる
- 短期的な売却よりも、長期的な活用を考えることで収益性が高まる場合がある。
農地の売却で気をつけるべきポイント
農地を売却する際には、法律の規制や税金、手続きの複雑さなど、多くの注意点があります。スムーズに売却を進めるために、事前に確認しておくべきポイントを詳しく解説します。
農地法の規制を理解する
農地を売却する際には、**「農地法」**が大きく関わってきます。特に以下のポイントに注意が必要です。
- 農地の売却には農業委員会の許可が必要
→ 農業を継続する目的で売却する場合、買主が「農業を行う適格者」でなければならない。 - 農地を宅地などに転用する場合は、都道府県知事の許可が必要
→ これを**「農地転用」といい、地目変更を行うには農地転用許可申請**が必要。 - 「農業振興地域内の農地」は売却・転用が難しい
→ 農業振興地域の指定を解除(「農振除外」)しないと転用できない。
✅ポイント
事前に農地の所在地を管轄する農業委員会や市役所に相談し、売却や転用が可能か確認しておくことが大切。
農地の売却価格を把握する
農地の価格は宅地と比べて安価ですが、以下の要因によって変動します。
価格が高くなる要因
✔ 市街地に近い農地(宅地転用が容易)
✔ 道路に接している農地(利用しやすい)
✔ 地目変更がしやすい農地(農地転用の手間が少ない)
価格が低くなる要因
❌ 農業振興地域の農地(転用不可)
❌ 接道義務を満たしていない農地(開発が難しい)
❌ 地盤が弱い、整備が必要な農地(追加工事が必要)
✅ポイント
- 事前に近隣の農地の売買相場を調査する。
- 不動産会社や農地専門の業者に査定を依頼すると、適正価格が分かる。
税金の負担を考慮する
農地を売却すると、各種税金が発生します。
① 譲渡所得税(売却益に対する税金)
- 売却価格から取得費(購入費用)や売却経費を差し引いた額に税金がかかる。
- 所有期間5年以下→約39%(短期譲渡)
- 所有期間5年以上→約20%(長期譲渡)
② 固定資産税の変動
- 農地のままなら固定資産税は低い(特例措置)
- 宅地に転用すると固定資産税が増加
③ 農地を相続した場合の相続税
- 相続税評価額は時価の80%程度(一般農地の場合)。
- **「納税猶予制度」**を活用すると、一定の条件で相続税が猶予される。
✅ポイント
- 売却前に税理士に相談し、税負担を試算しておく。
- 節税対策として、農地の貸し出しや分割売却も検討する。
売却までの手続きを把握する
農地の売却には、一般的な不動産売買とは異なる手続きが必要です。
✅ 農地を売却する一般的な流れ
- 農地の現状を確認(登記簿、地目、農地法の適用範囲)
- 農業委員会へ売却許可の申請(買主の資格を確認)
- 売却先の選定(農家、不動産業者など)
- 売買契約を締結
- 所有権移転登記を行う(司法書士に依頼)
✅ポイント
- 農業委員会の審査には時間がかかるため、早めに手続きを進める。
- 買主が決まらない場合、農地バンク(農地中間管理機構)を活用するとスムーズに売却できる。
買主とのトラブルを防ぐための対策
農地売却の際には、契約時のトラブルも発生しやすい。
✅ 主なトラブル例と対策
| トラブル事例 | 対策 |
| 売却後に「地盤が悪い」と言われる | 事前に地盤調査を実施し、報告書を用意する |
| 農地転用ができず契約が破談 | 転用許可を得てから売却を進める |
| 売却後に固定資産税が増えたと苦情が来る | 税金の変動を事前に説明し、合意を取る |
| 口約束で進めた結果、契約トラブルに発展 | 売買契約書を作成し、公正証書化する |
✅ポイント
- 必ず売買契約書を作成し、契約内容を明確にする。
- 口約束ではなく、司法書士や不動産業者を介して手続きを進める。
農地売却の成功事例
事例① 農地を売却し、宅地へ転用
岡山市のAさんは、農業を続ける後継者がいないため農地の売却を決意。
✅ 農業委員会に相談し、農地転用の許可を取得。
✅ 不動産業者に仲介を依頼し、宅地として高値で売却成功。
事例② 相続した農地を売却し、負担軽減
Bさんは、相続した農地の維持管理が難しく、売却を決定。
✅ 農地中間管理機構に相談し、買主をスムーズに見つけることに成功。
✅ 譲渡所得税の計算を税理士に相談し、節税対策を実施。
まとめ
農地の売却は、農地法の規制・価格の変動・税金・手続きの複雑さといった様々な要素を考慮する必要があります。スムーズに進めるためには、事前の情報収集や専門家への相談が重要です。
株式会社アライブでは、岡山地域密着をモットーに空き家、建て替え時の解体作業をおこなっております。是非!解体の事なら株式会社アライブにお任せください!
その他のブログ記事/ OTHER BLOG /
岡山で解体のことなら
株式会社ALIVEへ
木造解体工事、鉄骨解体工事、RC解体工事、内装解体工事、アスベスト除去、プチ解体工事まで
安心してお任せください。地域密着・スピード対応!
お気軽にお問い合わせください。
住所:〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘368-3(国道250号線沿い)
電話番号:0120-812-181
受付時間:8:00〜19:00
定休日:なし
株式会社アライブの
スタッフ/ STAFF /

完全自社施工
だから安心
解体の事は何でも
ご相談ください












